目次
ぶっちゃけ、疲れません?
相手の気持ちを察して行動するのって大変ですよね。うわ、あの人怒ってるのかな、今これ言っちゃまずいかな?今席たったら迷惑かな。周りに迷惑かけないな、って、いちいち気を張って疲れます。
というか重い。ぶっちゃけ、「なんで相手のお気持ちをいちいちくまなきゃならんのよ!自分の気持ちくらい自分でなんとかするもんでしょ!」といいたくなる時だってあると思います。
日本では割と昔からある考え方ですよね。相手を労り相手の気持ちを考えて行動しようって。小学校のころから道徳の授業だったりいろんなところで無意識に叩き込まれますから、ほとんどの人がこの感性は大なり小なり持っていると思うんですよね。
でも察するって言っても限界があって、何でもかんでも察することなんてできないし、自分に精神的に余裕がない時だってあるし。昨今ではポリコレだのなんだので多様性を尊重しよう、って発言をさらに絞って選ばなきゃいけない空気もあるように見えます。
なんだか令和に入ってますます縛りがきつくなってないか?おかしいなぁ。多様性を尊重するってこんなに疲れるの?しんどいんだっけ?思ってたのと違くない?もっとこう、楽だったり面白いものだったり、もっと前向きなものなんじゃなかったっけ?もっと夢ある感じだったような?
なんて思ってらっしゃいませんか?
多様性を尊重して「言いたいことも言えないこんな世の中」が加速しとるような気がしません?ポイズンなの?
いやほんと、なんかの毒みたいですよ。毒ガスの類かな?息苦しいし。
もう察しの文化って限界が来てるんでないの?ポイズン。
はぁ全然歌のリズムにあってないですね…ポイズンポイズン
自分と同じ思考や文化をもっていることが前提にあって成立してた文化
エスナ!ポイゾナ!キアリー!
な…なんのザキ!!(発狂
魔法みたいに簡単に浄化出来りゃ苦労しないんですがね…
で、この記事のテーマにある日本の察しの文化に戻るんですが、正直言ってもうその前提が崩れてきていると思うんですよね。
集団主義的文化のもとに個人を並列化して全体主義化された前提があった少し前の日本だったら察しの文化はうまく機能して、実際それでうまくいっていたと思うんです。
しかし昨今では、働き方改革や多様性の尊重、LGBTなど、SNSなどをはじめとして、社会全体で個人を尊重しようとする動きが始まってもう久しい。
SNSで一般の人が自由に発信できる場所が設けられて、昔に比べて自分が思っているよりも他人というのは自分と違うということに気づく機会も増えてきた。海外はいわずもがな、日本でさえ本当に世の中には実はいろんな人がいて、いろんな価値観や考え方があって、その中には自分では全く共感できなかったり、価値があるとは思えないようなことを信じていたり、やっていたりする人もいることがわかる。
自分が持っている価値観が全てなんてことは実は全然なくて、多くの価値観の中の一つにすぎないということ。そんな現実に気づきやすくなってきた。
自分と他人が違うということが世の中で少しずつ前提になりつつある今の世の中で、今後この文化はさらにどんどんうまく機能しなくなっていくのではないかと思うんですよね。
これまでは会話せずとも阿吽の呼吸で合わせることができていたことが、個人の価値観の違いの見える化、自身の価値観を尊重するという多様化によって個人の価値観がばらつき始めたために、自分と全く合わず、結果疎外感や孤立感のようなものを得られる機会が増えて、単純に疲れるだけのようなものになってきたんではないかと思うのです。
察するのやめたらあかんのか?
だったらこれからの多様化の時代を楽しく気持よく生きていくためにも、この察しの文化は変わった方がいいんじゃないでしょうかね?
察することを禁止するとかではなくて、察することを当たり前のことにすることをやめてもいいんじゃないかって。
それも多様性ある健全な社会を進めるプロセスの一つなんじゃないかって。全部個人の個性、表現の違いということでいいじゃん、って。
もっと面白い社会にしたいじゃないですか。窮屈でなんだか息することすら周りの許可がいるような激重な社会の空気なんかごめんではないですか。
どんな人のことも察する多様性ある社会なんかやりたくないじゃないですか。
自分にとって嫌な人だっているわけですし、合わない人だっているのにそんなもんにまで合わせろって要求にこたえてたらあぁもう気が狂うって!
そりゃ妙な犯罪も増えるってもんですよ…とち狂って仲間にザキを打つ人がいても不思議ではない…割と冗談ではない話です。だってほら、あるジャンそんな感じの事件。もちろん魔法の話しではないですよ。
人は他人のことを本当は理解できてない
根本的なお話なんですけどそもそも人に人の気持ちを理解することはできていなくて、察するって実はできているようでできてないんですよね。
なんとなく相手の気持ちを察っしたり、同じであるかのように見えたりすることって悪魔でそう見えているだけの話しで、自分の主観の話しでしかありません。
人は他人を自分の心の鏡にしてるだけ。そこに映った自分自身のことを考えることくらいしかできない。他人の内面を考えているつもりでも、結局は自分自身です。
ようは察しの文化は、”たまたまうまくいっていただけ”なんですよ。
みんな簡単にわかったつもりになれた。他人に自分の価値観を押し付けて「俺たちは一緒だ」なんて言って、言われた方も無意識にその相手に寄せてた。実際に均一的な価値観だったから寄せることもそれほど難しくなかったからできた。疑わなくて済んだ。それで人間関係を構築するのが当たり前にあったから、多分通じてたんじゃないかな。
でも今は違う。個人の価値観が伸びて結果横ぞろいになりづらくなってきた。必死に合わせてもおいつけなかったして、その上大した見返りもない。割とみんな潮対応だったりすることもある、他人に対する人々の関心も昔に比べたら随分低くなっているわけで、合わせるだけむしろ損しているだけでは?
やるメリット自体もそもそもなくなってきてますしもう無理があるってもんです。
「察する」のではなく、「聞く」
相手の気持ちを察するのをきっかけにすることは問題ないと思うんですよね。というか別にそれを禁止するという話ではなくて、察するのも察しないのも、個人の自由であるわけで。
でもそれを「しなければならないこと」にしていたらまぁ疲れて当然ってものです。
だからまずは察しあうことを前提とすることはまずやめることからなんじゃないかと思うのですよね。他人の気持ちくらいわかって当然、っていうのをやめるんですよ。ていうかわかってないんですから。
相手に察してもらうことを求めることをやめる。そしたら自分も相手を察する義務から解放できて楽になれます。
で次に、自分が思っていることを言葉にすることから始めたらいいんじゃないかと思うんです。そして、それができるようなったら相手に話してみる。次に、相手から話を聞くことを始めたらいいと思うんですよ。
単純にいうなら会話しよう、ってことです。ちゃんと話をしようってこと。相手を待ってないで自分が言いたいことを言うんです。
でも自分が思っていること言葉にするって、やってみると案外難しかったりするんですよね。途中で言いたいことが分からなくなったり、パニックになったりする人も多分いると思います。特に、察してもらうことを期待して生きている時間が長いほど、難しいと感じるんじゃないでしょうか。
だからまずは練習して自分の言いたいことを言葉にできるように少しづつしていくことから。それができてきたら、それを人に伝えてみて、会話をしてみるんですよね。
きっといろんな反応が返ってくると思います。会話に花が咲いたり、特に特別なこともなかったり、気を悪くしたりすることもあると思いますが、でもそれが会話の醍醐味ってもんです。こみゅにけーしょん。それがリアル。自分を自分で表現するんですよ。そうするとそんな風に現実の世界は反応するってことです。
それを受けて自分はどうしたいと思うかを考えて、相手に聞いたり問いかけていく。そんな風にまた繰り返し、自分を表現していくわけですよ。
そうしていけば、もう察し合うことも必要なくなると思います。それにこれって他人は関係ないのですよ。例え世の中の人が察することを他人に求めることをやめないにしても、少なくとも自分が察することを止めれば、自分のその問題は解決します。
察することを期待している人がそれで不快になるなら付き合わないという選択をすればいいだけですし、じめじめした人間関係も必要なくなります。判断軸が出来てよりフットワークも軽くなります。
そもそも他人をいちいち察するなんて過保護ってもんです。他人の世話なんてやかなくていいんですよ。自分の気持ちは自分で世話をしたらいいんですから。それができる人と付き合うことを選んだらいいんです。そしたらそれをしない人ともwinwinじゃないですか。
こんな風に、付き合う人を選ぶ自由も手に入れることが出来るんですよね。
…というわけで、察しの文化、やめますか?死にますか?察し or ダァーイ!?ハーン!?
というのは冗談ですが、やっぱり毎日幸せに楽しく生きていけるなら生きていきたいですよね。それが自分の思い込みの世界を変えるだけで得られるなら安いもの。自分が変わってしまうだけで幸福が手に入るのだから安いもの、自分の幸せのための投資だと思ってはじめてみるのはいかがでしょうか?
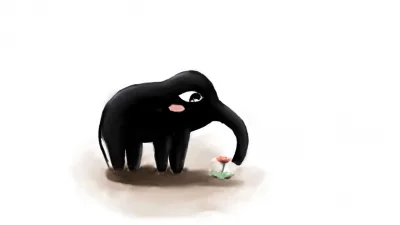
コメントを残す