「世間一般的な普通の人間でなければいけない」
「常に相手の言うことを聞かないといけない」
「他人に褒められることをしないといけない」
「他人に求められていることをしないといけない」
そんな義務感。他人ファーストな意識。
自分のやりたいこと、したいことよりも他人の都合が大事。
親、教師、上司など「目上」の人間、人によっては、身近な友人にすら、そう感じているかもしれない。
でもそんな必要はない。自分の心、人生を相手に従わせる必要はなんかないんだ。
それは全部他人の要求、他人の都合、社会の都合。
自分の都合とは違うもの。違うものをわざわざ同じにしようとしなくていいし、違うものをわざわざ従わせて否定する必要なんかない。
自分が思う自分だけの気持ち、価値観はそのまま持っていていい。その方がずっと人生は前を向く。
他人に否定され続けて卑屈になって生きるよりも、そんな他人からの支配から自分を解放して、自分の気持ちを許す。その方がずっと楽でずっと幸福だ。
目次
“自分の心を従わせる”ようなものなんて存在しない。
従うというのは、なんらかのルールに従う、ということだと思う。
多分そのルール、自分を無理やり従わせてくるかのように感じる何かっていうのは、とてつもない強制力があって、それにはひれ伏しておとなしく、自分を殺し続けるしかないんだ、と思うような何かなのかもしれない。
でもそのルールっていうのは本当にそんな力があるものなんだろうか?
そんな強制力のあるものなんだろうか?
単に誰かが言っていただけのことだったら?
「〇〇な奴は生きてる価値なし、〇〇できないやつはクズ。」
こんなのその個人の感覚と価値観の話しでしかない。この世の全員が賛同した何かでもなんでもないし、そんな数すら、問題ですらもない。
そこには何の強制力もないし、法的拘束力も何もない。だったら従う義理も意味もない。
自分がそう思わないならそれでいいんだ。それを「そうなんだ、そうじゃなきゃいけないんだ」なんて思おうとしている自分がいるなら、それは自分の素直な気持ちを否定して無理やり自分を納得させようとしている証拠。
本当はそんなこと毛ほどにも思っていないのに、「そうしないとやばいんだ」なんて本気で考えて、それに従わなきゃいけないと思い込んでいるだけの話だ。
よく考えてみればわかる。こんな人を下げて気持ちよくなろうとするような人の人生が幸せだと思うだろうか?人を下げないと自分の幸せを確認できない人の人生が幸せだと思うだろうか?
きっと本人は必至なんだ。多分自分が我慢していて、不満を抱えて生きている。そんな中で自分の人生を幸せだと思い込もうと、他人と比べて自分はマシだ、優れた存在だと思い込むことでそれを達成しようとしてそうした。
そんな人生のどこが楽しいの?そんな人生のどこが楽なの?我慢ばかり、苦しいばかり、その不満のはけ口が他人を見下すなんて言う行為なんて
だから聞かなくていいんだ。そんな後ろ向きな他人の言い分なんて。誹謗中傷なんて。むしろそんな彼らの生き方を参考にしてしまったら、自分もそんな彼らのような人生を送ることになってしまうかもしれない。
会社や学校のルールは?
会社の規則だったり学校の校則だって、別にそれがこの世の真理だとか、絶対であることでもなんでもない
その組織の中で決められた決め事にすぎず、いわゆるローカルルールなんだ。
其れと自分の考え方や価値観が違うからといって、自分を否定して抑圧する必要なんかない。単純に相性として考え方や価値観が自分と会っていないというだけの話しでしかない。
学校だったら我慢は必要になるかもしれない。無理に髪の色を染める必要はないわけだし、でも多分やりようはいくらでもあると思う。私の知人は洗えば落ちるカラースプレーみたいなものとか使っていたっけ…
地毛だったら地毛と言えばいい。それで信じてもらえないなんてことになったら、それはもはや人格否定的というか、存在否定、侮辱以外の何物でもないので、それはもうSNSで炎上でもさせちゃえばいいんじゃないか?自分に嘘が全くないなら、それは正当な行動だと思うし。
会社だったら、自分は選べるわけなんだかラ合わなきゃやめてしまえばいいんだ。会社なんて世の中たくさんあるわけだし働き方なんて今の時代たくさんある。
正社員が合わないなら契約社員やフルーランス。アルバイトでもなんでもいいわけだし、空いた時間を別の自分のやりたいことにあてて、楽しく生きていけばいいだけの話だ。
法律は?
法律に関しては守らざるを得ないとは思う。法律を破ったら犯罪者で刑事罰がつくんだから、やるメリットもほとんどない。
そもそもそれを追ってまでやりたいことなんて言うのは大抵、人から何かを盗んだり何かを壊したり、人を傷つけたりするかのような不健康な動機ばかりのもの
その動機の在り方は、自分自身の心が不健康だから出てくる欲求な可能性もある。他人や社会が憎くてそれでその仕返しみたいな気持ちでやっていたり、不満が原動力で行う行動というのは、自分を幸せにすることはほとんどない。
だったらそれはむしろ自分を変えた方がいいと思う。その方がそんな苦しい人生よりもずっと気楽で楽しい人生を送れる。
ルールは神様じゃない
でもそんなルール達はすべて人間が決めたもの。法律ですら人間が決めたものでしかない。そしてそのほとんどが他人が決めたものだ。
ルールは悪魔でルールにすぎず、自分の在り方でも人生でもないのだ。
ルールで決まっているから、では自分の人間性や価値観までそのルールに従わなきゃいけないということなどない。
自分の在り方を従わせるルールなどどこにも存在しない。
他人は神様じゃない。自分と同じ人間だ。
自分と同じように間違い、迷い、それでも生きている。
ルールとは、そんな存在が決めたものだ。
だからそのルールが”絶対に正しいことを言っている”という保証はどこにもない。
ルールは神の啓示でもなんでもない。ただの他人の作った決まり事、
そんな他人の作ったものに、守る必要はあることはあっても自身の身も心もその都合に染まり切らなきゃいけない義務などない。
「従属しなくていい」と自分に許可する。
だからそんな誰かや何かに従わなきゃいけないんだ、という従属思考は捨てていい
いらない。
他者に心を従属することに対する価値を捨てていい。
日常生活の中で様々なタイミングで顔を出す「他者への従属」の思考。
その思考をしている自分に気づいたり感じたたとき、それをやめてもいいと自身で気づき、その場で放棄する。
それを日々繰り返していく。そしてそれなしで新しく経験していく。そうしていく中で他者に頼らなくとも自身の中に安心感を感じられた、という経験ができるようになると、自身が他人を使って恐怖を作り出していただけだったいうことを客観的に自覚できるようになっていく。
その気づきこそが、他者を自分から切り離すことにたる理由、糧になっていくのだ。
「なんだ、他人なんて気にする意味なんかないじゃないか」
と、思えるようになっていたら自分自身に近づいた証拠。
「相手に気に入られることをしなきゃ」なんて、思わなくてよくなる。
その感覚を起点に、自分の意思ですると思ったことをするだけだ。
他者は自分の人生と最初から何の関係もない。親であろうがなんであろうが同じことだ。
親も自分以外の人間、他人にすぎないのだから。他者に従属する意味も必要性も、自身が生きている事実には何ら干渉してなどいないし、できない。
他人や他人の都合を自分から切り離していけば切り離していくほど、人生はとても身軽でシンプルなものになっていく。
人生のとらえ方は、シンプルであればあるほど生産的だ。自身の感覚だけで幸福を完結してしまえば、悩みなどなくなってしまうのである。
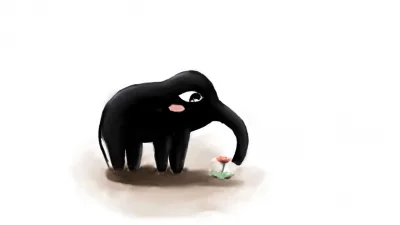
コメントを残す