「どうせ自分なんて…」「あいつは人間の屑」こんな風に自分を責めたり他人を責めたりすること人っていますよね。
私は昔はそうでした(もっぱら前者でしたが…)。これって衝動的な感覚に近いというか、例えば自分よりも優秀だったり綺麗だったりかっこいい人を見た時だったり、会社の仕事で上司や取引先との間でいざこざが合った時とか、どっちが悪い、正しいなんて言うような思いが起こると、ほぼ反射的にそう感じて考えてしまうというようなこともあるんじゃないかと思います。
ところでこの「どうせ自分なんて…」「あいつは人間の屑」っていうこの二つ、とても良く似ていると思いませんか?
え?似てない?言ってることが全然違うって?
確かに言っていることは違いますよね。でもやっていることは似ているというか、人を責めているという点が共通しているんじゃないかと思います。自分か他人か、その対象が違うだけです。
実際分析してみると驚くほど似てるんですよね。その共通点について書いていきたいと思います。
目次
白黒思考であるということ
どちらも「この世には絶対的に間違っていること、正しいこと、優劣がある」と思っていると思います。物事は全て割り切ることが出来て、世界はそれによって分断されたり、測量されたり、分別されたりする。
つまりこの世には絶対悪と絶対善、絶対的に優れているものと劣っているものが存在しているという風に捉えていて、例えば金持ちと貧乏とか、優秀と劣等というように何かとどちらが良くてどちらが悪か、という点で物事を見がちである、という点です。
実際の世界は、悪も善もあるようでありません。何を悪とするか善とするか、というのは宗教的な考え方にすぎません。
仮にある行為に善悪があると仮定したとしたとして「人に親切にすることは善か悪か」、という問いをしたとします。すると必ずしもこれが善とは限らないと思います。例えばある人の思う親切という行為がその行為の対象となる人全員にとっての親切ではない、ということもあります。お年寄りに席を譲ったら年寄扱いするな!と怒鳴られた、なんて話も聞きますしね。理由はわかりませんがそのお年寄りにとっては席を譲られたことはうれしくなかった、つまり善ではなかったわけです。
仮に法律を善悪としても法律自体時代とともに変わっていくものですし、権力者がその法律を”悪用”したりすることだってあります。その”悪用”の定義すらそれを都合が悪いと思う人にとっての”悪”であって単なる言葉の表現でしかありません。
少なくともその”悪用という行為”を働いた人間からすれば”当人にとっては利益ある善の行為”なわけで結局何が正しいとか何が悪いのか、というのは個人が見ている世界観の話にすぎないわけなんですよね。
優劣の問題も例えば美しさの基準なんていうのも時代とともに変化しています。今でこそ目の大きな女性は美しい、かわいいとされていますが江戸時代の浮世絵が流行ったころはまさに浮世絵のような女性が美しいとされていたと聞きます。
男性は今は背が高くてやせた人がもてますが、終戦直後は太った人の方がもてました。金持ちであれば幸福かどうか、という点についても金がありすぎて金銭感覚が崩壊したりいろんな人が集まってきた結果だまされたりもして人を信用できなくなって孤立に陥ったりすることもありますし、お金に不自由のなさそうな芸能人の中で自殺する方すらいる。まさに一長一短なわけです。
それにこんなのは所詮は統計的な話、一例的な話にすぎず一人一人にフォーカスすれば何を好み何を美しいとするのかなど、様々な基準がバラバラなためそれを真に定義したり測ることはできません。
物事ってその見方や角度、環境(自分やそこにいる人も含む)、人間関係の形によってまるで万華鏡がごとくころころ変わる性質を持っています。人の考える定義と現実というのはいつも同じというわけではなく、常に例外は存在し多くの場合でずれているわけです。ゆえに定的な答え、正解はなくてどこまで突き詰めても常にグレーで不鮮明な性質であることはかわりません。仮に会議や話し合いなどで何かを正解、間違いと決定する場合それは一種のその場における合意形成、妥協点のようなものであり真に正解とか間違いであることは意味しないと思います。
その性質を無視して本気で白黒で決めつけられると思っている思考が自罰的、他罰的な思考の元にもなっているんじゃないかと思います。この世には絶対的な善悪や何かの基準があると思っているからこそ完全な答えが出せる、それを自分は知っていると思っていてゆえに善悪の基準のみで物事の判断をするようになる、という感じですね。
この思考って交渉や相談ができないんですよね。妥協したり協力できるところは協力する、というようなグレーエリアがなく、0か1か、善悪の二択だけで余地がどこにもないんです。
自分と他人は同じ世界で生きているという前提がある
自分のとらえている世界観=この世の全て
白黒思考の話しと似たような話ですね。
この世の善悪を知っていてそれで割り切れると思っているわけですから、全てを明確に区別でき割り切れる(と思い込んでいる)。ゆえに全能感を感じていて、真に優れた何かを知っていてると思っているということもあるかと思います。
他罰的思考の場合は自分は善側の人間。だからこそ人を裁くことが出来るし、比較もできる。優劣をつけて仲間はずれにしたりもできます。
一方自罰的な思考は自分が悪側。自分は間違っていて、劣っている。だから自分はいつも正解の何かに合わせて生きていなければならない。周りに合わせて息を殺して叱られないように自分を否定して生きていかなければならないと思い込んでいます。
しかし「自分は世界の全てを知っているという思い込み」の点は共通しているんですよね。他罰的な人はわかりやすいと思いますが自罰的な人は自分は悪である、間違っているということに確信的であり、全能感ならぬ全”不”能感を持っているとも言えます。この世の悪や劣等が何であるかを知っていると本気で思い込んでいるわけです。
自分と他人が違うことは許されないと思い込んでいる
白黒思考による絶対的善悪、自分の思い込み=世界の全てという思い込みによって、自分と違う考えをもっている人なんているわけがないという思い込みもあrると思います。
「人間とはこういうものだ」「こんなこともできない人は人間の屑だ」と、自分が思う人間というモデルに自分とすべての他者を集約して考え、自分と他人は(自分が思う人間という定義において)同じであるべき、はずであるという一種の選民思想のような考え方に陥っているということもあるんじゃないかと思います。こう考えてみると日本の同調圧力の文化ってどこかナチズムっぽい側面があるのかもしれませんね。
自分と違う人がいないわけがないというよりも、いちゃいけない、という感覚かもしれません。他人と自分は同じでないといけないというルールを果たすことができなくなってしまいますから、それは自分の世界観を覆しかねないのでその間違いを正さなきゃいけないという思いに駆られてしまうのだと思います。
ゆえに自罰的な人は、自分が他人と違うとどこか自分がおかしいのではないか、普通ではないのではないかと不安になり自己否定に走ってしまうし、
他罰的な人は、自分が他人と違うと相手が悪い、おかしいやつ、異常だ、間違っているんだと考えて支配しようとしてしまうわけです。
他人のことを理解できていると思い込んでいる
他人と自分が考えていることは同じである、べきであると思い込んでいるため他人と自分は同じことを考えている、同じ思想である、つまり自分は他人のことを理解できていると思い込んでいるということもあるかと思います。
他人の考えていることを常に想像し、それを元に行動したり思考したりもします。パラノイア的な思考をもち、相手が言葉にしていないことを勝手かつ脅迫的な形で想像し決めつけたりします。
他罰的な人なら「何見てんだこら」とかけんか腰になったり「お前今俺のことを馬鹿にしただろ」といちゃもんをつけてみたり、自罰的な人なら「あの人はきっと自分のことを嫌いに違いない」と一人で思い込んで自分をどんどん追い詰めたりもします。
しかしそれは結局思い込み、人は人をその身体機能の限界的理由から理解できてはいません。だって相手の脳の中身を知るすべはないのですからね。脳で考えていることが外に出てくこともなければテレパシーのように電磁波か何かで伝わっているわけもないですから。
他人の頭の中に対して行う想像は全て自分の勝手な妄想、独りよがりな思い込みに過ぎない。それも自分の劣等感や虚栄心などを他人を鏡にして写しているだけ。要は自分自身を使った単なる妄想です。その妄想を他人自身の心だとどちらも信じているわけです。
間違いを恐れている、自信がない
白黒思考であるということは間違えることを非常に恐れているという側面があるということでもあります。他人と違うことは間違いであり、間違い=悪というとらえ方がり、結果必死にそれを避けたり、あるいは撃退しようとするんじゃないかとも思います。それが成功に対する執着心を生み出したり、逆に失敗を怖がって何にもチャレンジできない自分を作り出したりしています。
自罰的な人は消極的な動機を持ち、何事においても間違えないためにものすごく神経質かつ必死になります。病的な完璧主義にとりつかれたりしてそのおかげで精神的に参ってしまうこともあるんじゃないかと思います。
他罰的な人は間違える人をとてつもなく厳しく責めたり時には暴力をふるったりすることもあると思います。成功に執着し、他者に完璧を求め強欲になり手っ取り早く成功を収められそうなギャンブルなどに手を染め中毒化してしまうこともあるんじゃないかと思います。
何れにせよどちらも間違いという事象が許せない、という点では共通していると思います。それだけ間違えることが怖く、おびえているのです。
他罰的な人がおびえているというのは意外かもしれませんが、他罰的な人は怒りによって対象を圧し、執着によって何かを支配したり他人を屈服しようとするわけで、やはりおびえているわけです。子犬が大きな犬に吠えるのと同じですね。
どちらも他者に恐れを抱いている。恐ろしいと思う何かに対する反応が違うだけなんです。
「べき論」思考
また自分の素直な気持ちを正解や間違い、優劣というジャッジで封印してしまっているため、思考が〇〇すべき、なんて考え方にもなっていたりします。自分の欲求や気持ちが希薄だったり、それに罪悪感のようなものを感じてしまっていて、価値観の押し付け合いで苦しい思いをしてしまうこともあるのではないかと思います。
他罰的な人なら相手に、自罰的な人なら自分に対して何かを背負わせたり背負ったりします。いつもどこか生きづらく、疲れていたりイライラしていたりしますね。
最近の傾向としては例えばジェンダーハラスメントなどのパーソナリティを強要したりするのが典型じゃないかと思います。男らしさ、女らしさという定義を自分にも他人にも押し付けて、こうあるべき、こうでない人は生きる価値なし、付き合う価値なし、とまるでナチスよろしくの迫害をし始めてしまいます。
人は人を変えることが出来ると思っている
自分の価値観がみんなの価値観であると信じているのでそれを他人にも押し付けたり、自分に強制したりすることもあると思います。他人に対して自分の世界観を持つことが出来る、もしくは持っていて当然だから持つべきだと思い込んでいるという状態です。
他罰的な人の場合自分の思う正しさや善を使って人の人生に干渉して変えることが出来ると思い込んでおり、それが自分の使命だったり義務なんだと思い込んでいることもあると思います。メシアコンプレックス的な気質をもっていることもあるかもしれませんね。
自罰的な人の場合他人の正しさや善に染まらなければならないと思い、他人の都合に合わせた自分や他人の好きな誰かに変われると信じています。しかしいくら他人のそれに合わせたつもりになっても他人の気分はころころ変わるものですから限界もありますし、他人が本当に求めている人間像が何なのかというのは相手の頭の中をのぞくことでもできない限りにおいて不可能だと思います。
他人と自分は人生の積み重ねが全くことなります。成り立ちがすべて違うわけですから同じ価値観や同じ考え方をもつということは見かけ上では同じに見えることはあっても脳内の思考が全く同じとはとても言えない以上、それは不可能な話です。家族などの近しい人であろうと同じ話、脳が違うわけですからね。
本気で人が誰かの思う何らかの理想像に自分を当てはめようとしたら途方もない労力がかかります。それが「みんなに好かれる自分」だったとしたら、他人はこの世に70億人以上いるわけですから…どう考えても不可能でしょう。
罪、義務による支配関係が構築されることも
自罰的な人は常に正しくあろうとしますし、他罰的な人は自分の正しさを人におしつけて管理しようとします。
この両者って互いに強くひかれあう性質があって、結ばれると共依存の関係になってしまうと思うのですよね。自罰的な人は自分を認めてくれる人、コントロールしてくれる人(正しいことを決めてくれて自分を導いて安全を保障してくれる誰か)を求めていて、他罰的な人は自分の正解を押し付けられる人、自分の正しさを証明してくれる人、支配できる人を求めている。自罰的な人には他罰的な人が自分を守ってくれる救世主か何かのように見えたりして、強くひかれてしまうんじゃないでしょうか。他罰的な人は自分が優れているということ、正しい人間であるということを自身の支配下に置けた、分からせたと思うことが出来ることで間接的に自分を認めてくれる人を求めているので喉から手が出るくらいほしくなるわけです。
一方、白黒思考でない人とは合わないことが多いんじゃないかとも思います。自罰的思考の人の場合、コントロールしてくれないですし正解も与えてくれないために依存できないので長続きせず、他罰的思考の人の場合単にすぐ逃げられてしまうため続かないと思うんですよね。自立している人って他人からの支配も誰かを支配することも求めてませんから。
となると、必然的に続く人間関係の形の選択肢の数から考えても正解を与える側と与えられる側という見事なパーフェクトマッチな同じ世界観の人同士の彼ら彼女らというのはくっつきやすく、続きやすいと思うわけです。まぁその実情は、正解を押し付ける側と押し付けられる側なわけですけど。もちろん自×自、 他×他ということもあるとは思いますが。勝手な予想ですがDVなどの洗脳というのはこのような支配関係の構図の関係性がある故なのかもしれませんね。この人しか私を愛してくれない、この人なしでは私は生きていけない、この人は自分がいなきゃなんもできないから、なんていうのはそんな関係性における極端な思い込みとして典型的ですし、互いが癒着しているからこそ離れることが出来なくなっているものもあるんじゃないかと思います。
またこの両者の関係性の根源にある感情は恐怖にあると思うので、恐怖感情でつながっている人間関係、ととらえることもできるかもしれません。その恐怖を解消するため、安心するために支配関係で互いがつながっているので、自己矛盾的ないびつな関係になってしまいなかなか離れることが出来ない関係性なんじゃないかと思います。
他者恐怖の感情がそれぞれの形で表れているだけ
このように自分を責める人と他人を責める人には共通した心理のコアがあり、違うのはそれが自分に向くのか他人に向くのかという点だけ。
ということはそれがどこに向くかで変わってしまう可能性もあるわけで、例えば社会的な立場が変わったりすることで豹変することも多分あるんだと思います。家では高圧的なのに外に出るとヘコヘコしていたり、顔を使い分けて支配する側か支配される側を選んで生きていたり、とか。
ふむ、となると支配的気質な人同士は相性がいいということになるんでしょうかね?共依存の正体だったりするのかしら?私の両親で考えてみると母親は高圧的でしたし、父親は暴力的で仲もよくなかったのにどういうわけかわかれることはありませんでした。
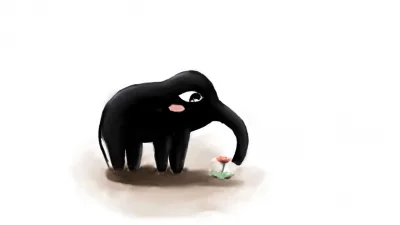
Elepanさん、初めまして。
ふと、「他罰的であることと自罰的であることの根本は同じかも」という考えが浮かび、ネットで「他罰的 自罰的」と検索してこちらのページに辿り着きました。
非常に思慮に富んだ文章で、言葉にならなかった自分の頭の中の考えをまとめることができました。
他の”心理理論”の記事も「承認欲求」についてなど興味深いので読ませていただこうと思っています。
お役に立てれば幸いです!