うまい絵ってどんな絵なんでしょう。自分がうまいと感じる絵でしょうか。あるいは、みんながうまいという絵でしょうか。
結構曖昧でぼやけていますよね。なんとなくそう感じるという程度というか、これでこうでこうでこうだからうまい、といちいち考えてまではしてない気がします。絵を見たその瞬間にただそう”感じる”かだけで思考的なものではない。無意識的で感覚的なものなんじゃないでしょうか。
では何をもってうまいとしているのか、何か客観的な指標はあるのか。その無意識の中に、あるいは感覚的に感じていることの詳細を明らかにすれば、そこにはなんらかの決定的なうまい絵の定義があるのでしょうか。
うまいっていうのはつまり「評価」ですよね。その逆に下手という概念があるわけですから。つまり優劣なわけですね。となるとうまい絵というのは優秀な絵、つまり評価される絵である、と考えることができると思います。
目次
評価される絵=うまい絵は真か?
では評価される絵とはいったいなんのでしょう。優秀な絵とはいったいなにか。デッサンでしょうか。デッサンが崩れてなく、正確なら評価されるのでしょうか。パースでしょうか。パースが正確であれば評価されるのでしょうか。配色の使い方か、カメラ角度がどの程度など数的に測定可能な何かを満たせれば評価されるのか。
上げていくときりがないと思いますが、結論から言うと、うまい、評価される絵の定義は人に依って違うものであると思います。その理由を説明していきます。
例えば、まず絵を見る側がどんな絵に興味を持っているかという点です。興味が違えば関心も違いますよね。ということは関心をもたれなかった場合、その絵は評価される、優劣の判断をされる機会すらないということになります。
その絵がどんなに精工でも、どんなにパースがきれいでも、どんなにデッサンが正確でも、どんなに配色がきれいでも、どんなにダイナミックな構図でも、どんなにかわいい絵であったとしても、それがその見る側の関心の範疇になければ見られないわけですから、あってないようなものになります。私で例えてみると、私はリアル絵が好きでアニメ絵はみません。ゲームのコンセプトアートみたいなのとか洋ゲーのリアル絵みたいなのが好きなんですね。なので自らアニメ絵を探して評価するという機会、関心自体がありません。
絵を見て評価する人はなにもきまったある一つのルールや評価基準に基づいてより優秀なものを求めているわけではないと思うんですよね。だってもしそうなら、上記の例の一つのデッサンが正確であればうまい、つまり皆がこぞって評価しに来る絵ということになるのならデッサンが崩れている絵はみな下手くそでだれも見向きもしない、ということになってしまいますが、デッサンが崩れていても評価されている絵はあります。
有名な絵画だとセザンヌの「りんごとオレンジ」なんかそうですよね。食器と布が融合していたり物体の距離感などがなく空間が歪んでいますが、特に中央の一つ転がってるリンゴだけはやたらとデッサンが正確で回りのゆがみの中で相対的に行き来と見え、その空間のゆがみによってどこをどう見るかによって印象が変わってくるという何とも不思議な感覚を感じる絵になっています。

が、この評価も人によって受け取り方はきっと違うと思います。まったく別の感想をもったり興味がないならとるに足らない絵と感じる人もいるでしょう。あるいはこの絵に対して有名であるとか、誰かに説明してもらえれば何かを感じるというケースもあると思います。
つまりデッサンが崩れていても正確でもうまい絵だと評価されうるし、その逆もあるわけですよね。それに他人からの説明などの別の要因もある。こんな風に絵の観測者である個人それぞれが各々独自のルールや感性、癖、それも無意識的な感覚に従って気持ちよくなれたり何らかのほしい感覚を得られる好みの絵を求め評価するのであって、評価される以前にその個人的な好み、目的というふるいにかけられちゃうのだと思います。
つまりいくら自分が思っているうまい絵、評価される絵という定義があっても、自分にとってはそうでも他人にとってはそうとは限らず、通用するかどうかはわからない、という事になるんじゃないかとも思います。
なのでもし自分の絵が”一般受けしない絵”であってもそれ自体は別におかしなことでもなく、なんなら自然的ですらあるといえます。
思考実験:どちらがうまいか?
ここでちょっと思考実験をしてみます。モナ・リザと坂本アヒル氏のずんだもんの絵を並べてどちらがうまい絵か、というアンケートをしたらどうなるのかを考えてみます。実際やってみたらちょっと面白そうですね。


どちらも比較的ジェネリック感のあるモチーフとして選んでみました。モナ・リザはともかくですが、ずんだもんを選んだのは動画サイトなどでよく目にする人気キャラクターだからです。とくに坂本アヒル氏のずんだもんは見ない日はありません。
さて、状況からイメージして考えてみます。人通りのある街頭で突然インタビューされ、2枚の絵を出されてどちらがうまいかと聞かれたらどちらを選ぶでしょうか。
多分モナ・リザを指す人が多いのではないか、と思います。
では次に日を跨いで、外出先ではなく自宅でずんだもんの動画を見ているときに偶然Web広告アンケートが流れてきてモナ・リザとずんだもんを二つ並べられた上で、「見たい絵はどちらか」を聞かれた場合はどうでしょうか。
おそらくこれは坂本アヒル氏のずんだもんが圧勝するんじゃないかなぁと思います。
おいおい「うまい絵はどちらか」が「見たい絵はどちらか」にすり変わってるじゃないか!反則だろ!と、思うかもしれませんがここでのポイントは「うまい絵、評価される絵なのかどうか」ということについてで聞かれ方はさほど問題ではありません。それを説明していきます。
この比較の総点は主に状況、環境因子の違いによる生まれる評価の差異についてです。バリエーションといった方が適格かもしれません。
人目があればそれを気にして選ぶということもあると思います。モナ・リザを選んだ方が知的にみられるだろう、という算段のもとに選ぶということもありえるともいます。
これは決してずんだもんを選ぶ人はバカである、ずんだもんをこのむことは幼稚であるという意味ではありません。この選択の意味は環境因子がおよぼしている影響のシミュレーションです。プライベート空間なら気にせず好きなものを選ぶこともあるかもしれません。面白い、かわいい、好きだからという自身の感性で選択する欲求が出しやすい環境だと、それに伴って選択するものも変わってくると思います。それがずんだもんだったのであれば、ここで選ぶのずんだもんであっても不思議ではないと思います。しかし全くずんだもんのことを知らなかった人が自動再生などの機能でたまたま動画を見た場合、特に関心がなければモナ・リザを選ぶか、何も選ばず広告をスキップもする可能性もあります。
また、それまでに何をしていたかという文脈もあります。街頭を歩いていた際と、ずんだもんの動画を見ていた時とではその時に抱いている関心に違いがあると思います。どこかへ向かおうとしている時に唐突にアンケートを求められた時、アンケートの内容と類似したコンテンツを視聴し、楽しんでいた時。全然違ってくると思います。またその時点での体調、気分、聞こえてくる音などそのほかの多くの要素が異なります。アンケートの聞かれ方だってその一つで、あらゆる因子や要因が影響を与えて評価を下します。
スマホの向こう側にいる人がどんな気持ちや目的、成り行き、きっかけでいいねをしたかはわからない、という話と同じです。
とはいえこのようなお膳立てをして考えなくとも、単純にモナ・リザを普段の生活の中で常々見たいと思っているかどうか、と考えれば少ないであろうことは容易に想像つきます。多くの人にとって一般的娯楽である動画サイトで大人気のずんだもんの方が確実に人気があるでしょうし、モナ・リザとずんだもんの二次創作絵のどちらが評価されるかを考えれば、その需要の圧倒的差から評価の機会、下地があるのはずんだもんなのでずんだもんであろうというのは想像がつきます。
となれば現代社会の日本に置いて考えると、評価される絵はずんだもんである、という事になるんじゃないかと思います。
これは別にモナ・リザが日本の現代社会においてはすでに陳腐化したゴミである、ということを意味するわけではありません。モナ・リザは依然として有名な絵画であり、日本だけでなく世界中の人に認知され、今でも生で見るには予約が必要ですし素晴らしいとされる絵には違いないと思います。(正直私も見てみたい)また全盛期にいたっては多くの人々を引き付けた絵画であったことは間違いなく、それが今でもこうして残っているというだけでもすごいことです。
しかしそれだけ「すごい絵画」であっても、そこに現代の美術の基礎にすらなっている様々な技術が構築されたものであったとしても、その人気が今も昔も変わらないかといえばそうではない。現代社会で日ごろからいつもモナ・リザを拝むほど好きであるとか、モナ・リザにまつわるコンテンツを毎日消費しているとかいう事があるかといえばそうではない。現代社会の普遍的な価値観、日常的な習慣、娯楽などの中で需要があり評価されているかというとそういうわけではないですよね。
にも拘らずモナ・リザは評価されている素晴らしい絵画である、と“されています”。街頭で「モナ・リザは有名で素晴らしい絵ですか」と聞いたら多くの人がYESと答えると思います。しかしその大多数のYESと答えた人が日常的にモナ・リザを見ているほど「好きか」というとそういうわけではないと思います。
おそらくモナ・リザという絵画を「好きか」と質問したら、多くの人が「別に好きでも嫌いでもない」と答えるんじゃないでしょうか。
要はほとんど興味がないのです。興味がないのに、好きでも嫌いでもないのに状況によってモナ・リザは”素晴らしい絵画だと評している”というケース。自分の感性は違うと感じていても、何も感じていないとしても無意識的に社会的な空気、要望、目を意識したものに自分の意見を表層上でカスタマイズしてそう評する。平たく言うと、その場のノリで評価しているということになります。
故に絵にほとんど興味がない人がみたらおそらく指すのはモナ・リザなんじゃないかとも思います。
この場合は大抵絵の技巧的な部分をほめる傾向にあると思います。この傾向はそのコミュニティの基本的な価値観によって決定されると思います。例えば日本という国で考えるならほぼすべての国民がうける義務教育の内申表的な価値観、共有されている社会的評価を念頭に置いた査定をベースとしたものの見方を用いるだろうと考えると、絵に対してありがちな感想としては「下手か上手いか」が真っ先に思い浮かぶと思います。ほかにも「社会的信用を得ている何か」など、優秀さという定規で測ることが絵に対するもっともコモンな認知だと思います。
「ネット上では評価されないが現実では「絵うまいね」といわれる」、というのは絵描きあるあるとしてよく聞く話ですが、社交辞令である場合を考慮してもその多くはそもそも絵に興味がないからで、結果としてコモンな優劣による感想をもつことになる、という事もあるのではないかと思います。
つまり。絵にほとんど興味はなくても「うまい」と評価することはできるわけで、絵に興味がない人に絵を評価される、というのは矛盾している感じですが、これの意味しているところはつまりこの人たちはうまい絵を描いてほめられたいと思っている人が欲しているうまい絵を描いてほめてくれる人たちではないんじゃないかと思います。なぜなら、絵を見たいと思って絵を見ているのではなく、たまたま目にしてそう思っただけというただの「反射」にすぎないから、
自ら出向いてまた見に来てくれるお客さん、自分の絵を「好き」といってくれる定期購読者ではないからです。
何なら興味がないほどうまいという評価になる、なんて感じかもしれない。これは私自身覚えがあって、例えば興味がないアニメ絵をみても「きれい」「かわいい」と思うことはよくあります。でもそれを自発的に追いかけたいというところまではいかなくて、いいねはしても、フォローすることは稀かなと思うんですね。元々あまり人の絵をみる機会がないのでフォローすること自体があまりないんですが、ファンになるレベルの「好き」でないとしないというか。でもいいねされた相手はそれをひょっとしたら重く受け止めていたりするかもしれない…ちょっと複雑ですね。
(評価の表現は人それぞれですからうまいという評価がだめとか失礼、ということは全く意味しないです。)
モナ・リザのうまれたルネサンス期に限ってみても技巧が称賛されたのはやはり文脈があります。宗教改革から始まった古典的なものを模倣して描くスタイルからより優れたものを生み出そうとするスタイルへの運動という流れがあり、旧来の形式的なのっぺりとした絵から生命力あふれるリアリティある絵を求めたという流れがあったようで、やはりそこまでに至る文脈があったのだという事が分かります。
自身のコンプレックスを解消するために評価する例
このような例の他にも、例えばある「コンプレックスが強い絵描きの人」のケースで自分の絵より素晴らしいと感じる絵を無意識的に避けて、自分と同じか下だと感じる絵を評価し、人間関係を作るという人もいるとかいないとか。「自分が一番うまいように感じる環境」を演出する目的でSNSなどで評価やフォローするというケースがあるという話。このようなケースの人が、その内輪の中で突然絵がうまくなっている人がでてくると激しい嫉妬心に駆られてしまいミュートしたりブロックしたりしてするなど、自分の世界から遮断するという動きをすることもあるのだとか。
他にも人の数だけ評価する目的はあると思います。その内容は決して好ましいものばかりではないのだとも思います。
そしてその内容はわかりません。誰も他人の頭の中はわからない。それがスマホの向こう側の顔も知らない人であればなおさらです。そしてさらに、どんな目的で評価されていようとそれをどうにかすることはできない。他人がどういう目的で評価するのかというその意思、目的そのものを支配することはできない以上、それがどれだけ好ましくなくともそんな自分の意思は他人の意思とは関係なく、一切の力を持たない。いくら自分がどんな絵を描いても、それ自体は変えられない。ただそれぞれの目的に従って評価したり無視したりするだけの話だと思います。
つまり、人が抱いている「他人から評価されること」という概念の全容は全てその個人の思い込みにすぎない、という事になるのだと思います。
単純にうまいだけの絵は別に求められてもいない
仮にデッサンなどの技巧的な要素をすべて満たした絵が存在すると仮定しても、それ自体に需要がないんじゃないか、という気もします。
というのは、現在もっとも絵が安易にかつ大量にもてはやされている場所はSNSでしょうが、そのSNSで共有されている絵は2次創作だったり漫画だったりネタ絵だったりと絵のクオリティ云々よりも何等かのコンテンツ的文脈を含むものであったり現場猫などのミームを使ったコミュニケーションツールとして使われているケースがより支持され人気であるからです。静物デッサンや写真模写が人気があるようには見えません。
うまさではなく、何らかの目的で使えるか、おもしろいかとか楽しめるかという点で需要、評価があるんじゃないかと思います。モナ・リザが生まれたルネサンス期に求められた写実性のように技巧的なものがもてはやされたのは、同じく時流の問題でしかなくはやりの一つであって評価される絵として確定的な要素というわけじゃない。現代社会であればその価値は少なくともメジャーなものではないといえそうです。
ただ単にうまい絵(精工に描かれた絵)では文脈もコンテンツもコミュニケーションもクソもないため魅力を感じず、関心を持たれず評価もないのではないかとも思います。
オリジナル絵は基本評価されないもの

例えばこの絵をみても特になんにも思わない、感じないかと思います。私の描いたオリキャラなのでそう思うのは至極当然のことですね。私にとってはわゆーてしゃーないどやちゃんでも、子供は自分の子供が一番かわいいのと全く同じ理論で他人様からみたらどうでもいいか、ぱっと見の「不気味」の一言に尽きると思います。
この赤道と北極並のキッツイ温度差は至極当然の話、ここにも文脈が関係してきます。
オリジナル絵は自分でキャラクター像や世界などを考えて描くので自分はその文脈を良く知っています。どんなキャラクターでどこで生まれて何をして何を考えて生きてきたのか。キャラクター一人でもいろんな設定が盛られたりします。しかし、他人はそれを何一つしらない。思い出も何もない故何も感じるところがない。
例えるなら2次創作は分厚い一冊の挿絵付き小説で、対するオリジナル絵は自分とは縁もゆかりもない他人の赤ちゃんの写真です。もし無人島に一つだけ持って行けるものをこの二つから選べ、と言われたら、99.9999%の人が前者を選ぶでしょう。人気の本ならなおさらです。
SNSでも同じようなもので、わざわざオリジナル絵を探そうとする人はほとんどいないはずです。有名な1次創作か2次創作を探す人がほとんどで、無名のオリジナル絵などは見向きもされなくて無理はないないのかなと思います。
故にオリジナル絵はいくら絵を練習うして技巧を磨いても需要の側面から評価にはつながりにくいのではないかと思います。需要の高いジャンルの絵(2次元美少女絵など)を描けばまだチャンスはありそうですが、努力と評価が比例しないケースとしてありがちなものになるのではないかと思います。
とはいえ、やはり時流などの環境や状況によって変わってくると思うので実際のところはわかりません。ですが、それは努力しても評価されることは保証されてるわけじゃない、という事は癒えそうです。
「うまい絵」「評価される絵」は定義として破綻してる
評価というものはそれ自体が主観的かつ個人都合的で無意識的なもので感覚的な判断によるところが大きく、かつ流行などの時流にも左右され、多くのお膳立て、文脈が必要で何ならようやく評価を得られてもその中身は大して関心もない可能性もあるなど常にブレまくってかなりいい加減で適当な一時的なものなんじゃないかと思います。
有名だとされているモナ・リザですら実際的な関心はこれだけ風化して時流の流れには逆らえなかったようですし、いかなるどんなすばらしい評価もやがては風化し塵も残らなくなるのだと思います。
評価の本質は一種の「流行」で、定的な真実のような一つの答えのようなものではない、「流れ」「偶然」「成り行き」「走り書き」「火花」ようなもので、つかみどころがなくすがれるところもなく、自分の意思ではどうにもならないなにか。故にうまい絵も評価される絵もこれだ、という定義ができず、人々の思い込みの集合体でさまざまに形を変え境目がないグレーな濁流のようなものである、という感じになるのかなと思います。
おそらく絵が評価されている人というのは、本質的に優秀な絵を描いているとかそういうことではなく、この濁流の中でたまたま波に乗っているサーファーのようなものなんじゃないかと思います。人は人を変えることはできない、という話を聞いたことがある人も多いんじゃないかと思いますが、それと同じで、人は他人の好みや趣向を変える力は持ってません。つまり、たまたま濁流の中でその人の好みと出力する絵がマッチした、という感じなんじゃないかと思います。
そしてその波は気まぐれなものですからいつ終わるかもわからない。昨今ではコンテンツは消費されるもの、なんていう風に言われる嫌いもありますよね。それだけコンテンツにあふれている世の中であるということもありますが、それも大きな濁流の形態の一部であると思います。いつその流れが変わったり終わるとも勢いを増すともわからない以上、ほぼほぼ運であるともいえるんじゃないかと思います。
つまり売れて神絵師になれるかどうか、というのはもろもろの要素を含めて考えても運である、と言い切ってもいいんじゃないかと思います。
なんなら「うまい」というもののとらえ方自体が教育などの外部的要因によるものによって作られた文脈由来の思い込みの概念に過ぎないかもしれないということも考えると、もはや「うまい」「下手」という考え方、とらえ方自体が作り物であり妄想なのかもしれません。
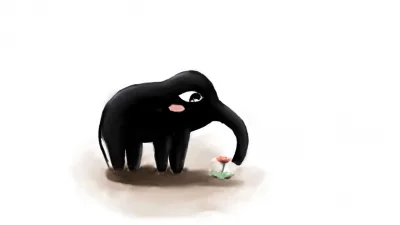
コメントを残す