この記事は以下の記事の続きのようなものになります。もしお読みでない方であればこちらを読んでいただくことをお勧めします。
「他人はいない」というのは私にとっては母親はいない、というものだった。常に母親の影が何をするにもあった。それは何をするにも母親が介入し、私を否定し、世話を焼き、しかし激しくしかりつけ、飴と鞭で懐柔することで常に母親の見方であるように仕向けられてきたからだと思う
常に母親の顔をうかがい母親に何とかしてもらうその人生観は、常に他人の顔をうかがう人生観へと発展し仕事も趣味もどの何かにもその影がちらついて何をするにも自信が持てず、最終的な裁量をすべて他人にゆだねてしまうようなほどに私の世界は全て他人で成り立っていたといって過言ではなかった
しかしその他人がいない、すなわち母親はいないとするとどうだろう。
この世界のどこを見渡してもいたはずのそれはいない。それはとてつもなく空虚でさみしいものだった。
目次
最初は到底受け入れられなかった。それだけ依存していた。
でもそれは彼女がいない現実を受け入れる準備ができていなかっただけ。親のいない世界で、何も寄りかかるところがない世界で生きる心の準備、すなわち精神的自立ができていないからというだけで、これができると受け入れることができてしまった。
人間は一人では生きられないという話はあくまで俯瞰的な経済的理由の話であって、精神的な話とは無関係だった。精神的依存を肯定するためのただの詭弁だったんだと思った。他人はいなくてよかった。いなきゃいけないと思い込んでいたけれど。結局は全部思い込みだったのだと思った
誰もいなくなった世界はただただ静かだった。あれだけ”うるさく”、”鬱陶しく”、”じめじめ”とした形容しがたい何かが世界を跋扈していた、その視線、ノイズ。巨大な恐ろしい形のない何かに監視されているようなざわつきが全く感じられない。
道を歩けば聞こえてくる雑踏、車がアスファルトを走りぬけていく音、近くの小学校の子供たちの声、すれ違う通行人たちのたわいもない会話…
そういうもののすべてにその影がなくなると、取るに足らない無意味なものになった。
でも代わりに、「感じられるようになった」
空気の味やその感覚、匂い。太陽の日差しの色に、それを受けて光る植物の葉、風に揺られてか擦れ合う音。
目や肌、耳で感じるいろんな感覚に「味」を感じるようになった。今まではそれが当たり前でどうでもいいとほとんど存在しないようなものだったのに、それがまるで逆転してしまったかのように変容した。
ずっと気が気じゃない毎日で時間の感覚も随分おかしくなっていたこともその時に気づいた。まるで時間が自分をせかしているかのようで、時間という概念にすら他人、母親の影がいた。それがとてもゆっくりと感じられ、現実感を感じられるものになっていった。
それが、自分の新しい世界のすべてとなって「満ちた」
それから人生の中で楽しむコンテンツも変わってきた。昔は面白い刺激的なものを求めていたけれど、今ではもっと日常的で取るに足らないけれど美しい、町の雑踏動画なんかが好きになった。仕事も趣味もマイペースでできるようになり、無理をしたり背伸びをしたりしてするようなこともなくなっていった。SNSもほとんどやらなくなり、これまでの様々な習慣はその時間に対する焦りの無意識が刺激を求める中毒の原動力になっていたんだという事にも気づいた。
世界は理解するものでもすがるものでもなく、ただ感じられるものだった
ずっと世界におびえ、その世界を必死に「理解」しようとして、決めつけようとしていたけれどそれはうまくいかなかったし、不可能でもあったし、何よりつらかった。いくら理解しようとしてもそこに潜む母親は自分を許してはくれなかった。何かを言えばそれに対する批判は当然のごとく出るし、どんな答えにも批判は必ずある。何を応えても、どんなに正解だと確信している何かを定義しようとしても、他人は、母親は一向に許してくれなかったからだ。
でも世界を「感じられる」と、ただただ広かった。今までどれだけ小さな点が如き穴を必死に理解しようとして、その穴の正解の形をみつけようとして、そこに自分を無理やりねじ込もうとしていたのか。それがよくわかった。
自分はとても小さくて、世界はとても大きくて、自分がいてもいなくても何も気にしないけれど、自分から何かを奪いもしないし強制もしない
ただ世界がそうあって動いている。意味もなく、しかしそれは秩序だっていた。
只感じるだけで満足できる世界は全てが満ち足りてた。
つまり他人、「母親という教祖」はこの世界に必要なかったのだった。
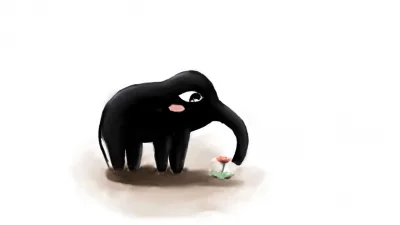
コメントを残す