Roni (sinceSpring2013)さんによる写真ACからの写真
何かに集中しようとしても、いつも気が散ってしまう。
ほかの娯楽が気になったり、SNSが気になったり、とにかく何かに集中するには誘惑がたくさんありすぎて、いつもそちらに手が伸びてしまう。
結果全く集中できず、進めたいと思っていたことも進まず、悶々と時間が過ぎていく日々。
そんな日々を送っていると「ちゃんとやらないと」「なんで続かないんだ」と自分を責め始めて、無理やり自分にやらせようとしようとする。
でもそうすると、余計に続けることが嫌になっていって、さらに続かなくなり、最終的にはそれをやめてしまうことすらある。
そんな悪循環に陥ってしまう。
私はそんな悪循環の中でもがいていた口だった。それはもう毎日が楽しくなくて、欲求不満と焦りだけが蓄積していく毎日。
「このままじゃ自分は何一つできずダメになってしまうかもしれない」「人生詰んだ」なんて思っていた。
でもその焦りも、今はなくなっている。
自分を強制せずとも自然に、苦痛も焦りもなく目の前のことに取り組めるようになった。
その秘訣は、「自分の気を散らせる外に対する関心の正体」を突き止め、それを捨てることでできた。
その関心の在り方。私の場合は、その正体が「気にする」だったからだった。
目次
「気にする」という認知そのものがいらなかった
「気にする」っていうのは、外の何かに注意を払っているという感覚だと思う。上記の記事で書いているのだけれど気にするっていうのは何かが怖いからやっていることなんだ。
つまり外の何かを気にしていて集中できないという心理は、外の何かが怖いからなんだ。
そして怖いというのは、案外ただの思い込みで、気にすることさえやめてしまうだけで解消してしまうようなものだったりすることもある。
例えば友達にどう思われているのかを気にしても、別にそれで何かが変わるわけじゃない。自分が友達の頭の中を疑おうが疑わまいが、その友達の頭の中に干渉できるわけではないし、それで何か影響を与えられるわけではない。
気にすれば備えられるかといえばそうでもなく、友だちが嫌いだといえば嫌いだし、好きだといえば好き。それ自体を気にすることで変えることはできない。ただ気にしただけこちらが疲れてしまうだけ。気を使って接するなんていうのは自分が疲れるうえに自分に嘘をつくだけで、何もいいことがない。
いいことがあると思っておそらく気にする、ということをやっているのだと思う。でも案外、その気にするって行為は損することの方が多い。
だったらその気にするっていうのは捨ててしまった方がいい。そして捨てるだけで、その友達に嫌われることが怖い、という恐怖は必要なくなる。
そうすると不安因子が一つ解消されたことになって、ほかのことに意識を回すことができるんだ。
それをいろんなほかの気にしていることにやっていけば…
最終的には目の前の集中したい自分ができあがる。
「気にする」という認知、あり方、考え方そのものを捨てる
「気にする」っていうことをもとに、かかわっているもの、携わっている様々ななものたち。人間関係の在り方やツールの使い方、勉強、仕事の取り組み方など。
気にして付き合っている友達。気にしてみている情報サイト。気にしてやっている仕事のやり方。
何かに執着している自分の考え方。あり方。
そういうものたちを捨てる。気にするという関心の持ち方をそのものを捨てること。
そうすればもう「気になるもの」なんてなくなる。外に引っ張られるかのような感覚は消えて、目の前の自分の純粋な「すること」という関心事だけが残る。
一種の“リセット”にすらなるのかもしれない。何かを「気にする」ことで築いてきた様々な関係がもしこれまでの自分の関心事や関係の大部分を占めていたとしたら、それを捨てることはとても大規模な断捨離になることを意味する。
でもそれは、それだけ今まで自分が自分に重い枷をつけて何かを背負って、生きづらさを感じながら生きてきて来たという証拠でもある。
それを全部捨てることができるということでもある。自分の苦しみ、生きづらさ、息苦しさ、そういうものの根源をすべて捨ててしまえる。
そしてそれさえ捨てれば、あらゆるしがらみから自分を解放することができて、自分に素直になることができる。
その素直な自分でいろんなことに興味をもっていろんなことにチャレンジしたくなる。そうやって目の前に集中することができるようになっていく。
目の前の自分のやることしか残らず、安心してそれに取り組む心が整うんだ。
どうやったら捨てられる?
とは言え、多分恐怖や不安に駆られて「気にする」ということを実行してしまっているので、それをいざ捨てようとしても難しいかもしれない。
恐怖は人に簡単にいろんなことを強いてしまう感情だから、それを手放そうとしてもなかなかできない。気にすることを捨てること自体が、おそらく既に怖いと感じることだと思う。
それで今まで自分の人生がうまくいってた、そう感じているかもしれない。そうだとすると、余計にそれを手放すのは怖いと思うから。
でもそれも結局は思い込みなんだ。だってその気にするっていう自分の行為は、現実の世界に何ら影響を与えてはいなかったんだから。
そしてその恐怖は、承認欲求という、恐怖で成り立っている欲求から来ているものなんだ。
これを捨てないことには「気にする」という認知は捨てることはきっと難しい。何かを強いて何かをしようとする、何かに強いられて何かをしようとするその考え方は、それを強いる他者の存在があって成り立っているもの。他者という存在を、どこか自分にとって絶対のような存在としてみてしまっていて、その人たちの期待を満たすことしか自分はしてはいけないという意識が、自分に何かを強いるという考え方をさせている。
「やらなきゃいけない」「しなきゃいけない」
そんな風に自分に何かを無理やり強いて何かさせようとするというのは、承認欲求由来の考え方、あり方なんだ。
だからその歪みを捨てて、自分に素直な気持ちで事に当たること、自分の自由を自分で許して、健やかに生きる人生を手にすることが肝心。
他人という恐怖を捨てること。孤独に対する恐怖の思い込みを捨てること。
それができて初めて、「気にする」は辞められる。それができて初めて、心を安静にして、健やかに目の前のことにマイペースで取り組むことができる、目の前のことに集中できる自分が手に入るんだ。
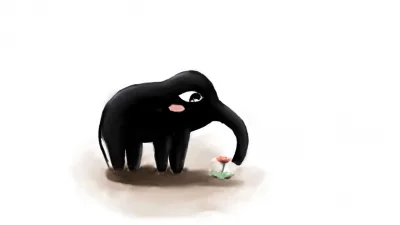
コメントを残す