承認欲求は人の本能だとか、誰しもが持つ自然のものといわれていることもある、日本人にとっては普通だと思われている欲求だと思う。
でもその理屈で行くとこの世のみんなが承認欲求を求めて生きている、ということになってしまうのだが本当にそうなのだろうか。
それだとみんなメンヘラってことになってしまう。他人に愛されたくて好かれたくて行動するなんていうのはまさに依存の思考で、それが人間の普通だったとしたら人間は随分不健全な生き物だということになってしまう。
それが本当なら全人類不幸説なんてものすら浮上してきそうだ。
そんな承認欲求が本当に本能?求めざるを得ない、どうしようもないものなの?
かつて私は「承認欲求お化け」だったと自認できるくらいには求めていたクチなのだけれどそれを捨てることができた今、それは本能でも普通のことでもないということがよくわかるんだ。
なのでこの記事では承認欲求が一体何だったのか、その正体を私の経験から描いていきたいと思う。
目次
承認欲求の根本にあるもの
承認欲求は他人に対する恐怖、義務感からくる「他人に褒められないといけない」「求められないといけない」「他人にとって価値ある人でないといけない」という欲求だった。
自分に素直な欲求ではなくて、自分にわざわざ他人を使って無理をして「無理やり求めさせている欲求」なんだ。
承認欲求は一見、自分の意志でほしくて求めているかのように感じるかもしれないけど、その求めているって感覚は「焦がれるような衝動的なものに近い、自分では抑えようがない強烈な欲求」であると思う。
だから承認欲求はよく「人間だれしもが持つ普通の欲求」「本能」だといわれているんだと思う。
それは正確には少し間違っているんだ。性欲や食欲というような、承認欲求というもの”自体”があるわけじゃない。
「承認される」というのは認知の話であって、自分の頭で考えていることなのだから、考えなければ存在しない。認知しなければ存在しないんだ。
最初から自分が知っていることなんかじゃないし、生まれつきそれを求めるようにして最初から持っていたものでもない。後天的に周りから学習したものだ。
本能と思ってしまうポイントは承認されるされないという認知の問題じゃない。それを欲する強烈さ、衝動、感覚自体が、本能だと言わしめる何かだ。
その正体。それは何かというと、恐怖なんだ。
他人が怖い。他人に嫌われるのが恐ろしい。
嫌われて独りになるのが怖い
だからその恐怖を取り除き、安心するために求めている。
自分の周りに脅威があるから、その脅威を取り除かないと自分の命が危ない。
とてつもなくヒステリックな感情だ。
そんな心理状態で求めている、非常に切迫したつらい欲求なんだ。
恐怖は人を最も苦しませ、迷わせる原動力
恐怖という感情ほど、自分を脅迫的に駆り立てて、それ以外に考えることができないようなことになるものはない。
人は恐怖を感じると、いの一番にそれを排除したくなる生き物。
どんなにお腹がすいていても、どんなに忙しい生活に追われていても、
例えば突然強盗が押し入ってきたらすべてを投げ出してそれに対応しようとしてしまうように、それだけ強烈に、自分を反射的にかりたてるもの。
それが恐怖。そんな恐怖を感じていたら、思考もままならない。正気を保ってはいられず、落ち着いて考えることもできなくなる。
恐怖は人を狂わせる力をもつそんな感情だ。だからそんな状態では承認欲求を本能だと思ってしまうのも無理はないことなんだ。
他人、孤独が怖いから
ではなぜ、そもそも自分が独りでいることはダメなことだと否定してしまっているのか、なぜ、他人に好かれている自分でないとだめなのか、愛してくれる人がいないとダメなのかというと、
それはやはり他人が怖いからなんだ。孤独が怖いからなんだ。すべての世の中の人に対して、平均的に、日常的に、無意識的に恐怖を感じているから。
だからその怖い他人の中から一人でも怖くない他人、自分を加護してくれる人を見つけるために、他人に好かれようとしたくなる。
自分を孤独にさせない、自分をほめてくれる人、好きになってくれる人を衝動的に求めてしまうんだ。
「自分と同じ他人」が唯一の”セーフゾーン”
自分を好きな人という唯一のセーフゾーン。それ以外の他人は、怖い危険地帯なんだ。
日常という巨大な世界、自分と違う、自分のことをどう思っているのかわからない無数の他人という存在で埋め尽くされた世界の中に、点のように小さく貴重な、自分を愛してくれる、好きでいてくれるという安全地帯という他人。
例えるならこれは一面が猛獣だらけで、そんな中たった一つの区画だけセーフゾーンがあるような状況のようなもの。
そこにしか自分が生き残るすべはない。そこしか安全な場所はない。
だとしたらすることなんて一つしかない。その場所の確保に必死になる。執着する。その人に守ってもらう以外に自分が生きていける術はないと感じてしまうから。
他人というセーフゾーンの確保に神経質になる
だからこそそんな希少なセーフゾーン、自分を理解し、自分を愛してくれる他人という保護者をなんとしてでも確保し続けなければ怖くてたまらない。
故に相手に自分と同じであるということを神経質に、強烈に求めて続けてしまうこともあるかもしれない。同じであれば、さらにそれを強固に確保できるような気がするから。
それゆえに常に自分の思ったとおりの考え方や行動をしてほしいと感じてしまうこともあるかもしれない。
それゆえに常に愛されること、好かれることといった他人の都合に由来するものを強く、脅迫的にその相手に求めてしまうこともあるかもしれない。
それはもう、まるで窒息でもするかのような感覚で。藁にも縋る思いで。衝動的に。脅迫的に。
依存という恐怖に駆られるこの承認欲求は、これほどに強烈にもなりえる。神経をすり減らし、憔悴しきってしまうほどに。
心身ともにボロボロになりながら、しかしその依存の中毒性故にやめることができず、ズブズブと依存の溝を深めていってしまうのである。
あるいはこんなケースも
相手が自分の知らないだれかと仲良くしていたりすると、自分のセーフゾーンが奪われたかのような気がして、激しい嫌悪感、不安感を感じたりすることもある。
裏切られたかのように感じ、恨みを抱いたり、激しい嫉妬心を抱いたりいて保護者であったはずの人すら敵になってしまったかのように見えたりする。
「今私以外の人見てたでしょ」と嫉妬してしまうのも、そういう心理から来ているのかもしれない。
他人を支配したくなったり、されたくなたったりもする心理
そのあまりにも強烈な感覚で求める欲求は、他人にそんな”自分の思い”を強烈に押し付けたくなったり、逆に他人の思いを自分に強烈にならわせようとしなければならないと感じたりすることもある。
それも前述の他人に自分と同じを求める心理からで、他人と同じ自分にするため。
他人を思い通りに支配しようとするか、自分が他人の思い通りになって支配されるかのどちらかをすることになる。
依存は時に支配にも変わっていってしまうものだ。あるいは依存はほぼ支配と同じか、同時に存在する二面性のようなもので、似て非なるものといってもいいのかもしれない。
同じ、コアに他人に対する恐怖があって、そこから出てくる発想だから。
支配しないといけない。支配しなければ自分が攻撃されてしまう。支配して屈服しなければ自分が否定されてしまう。
他人という恐怖を支配しないと、自分が危ないから、恐怖で衝動的にかられてそうしてしまう。
そうやって支配されたり支配したりをする関係性、義務を強いたり強いられたりする関係性を様々な他人と構築するようにもなる。
だから常に他人の目が意識にある
だからもし他人が自分を見たらどう感じるか、どう思うか。ということを考えずにはいられない。常に他人によく見られている自分を求めているから。自分を支配してくれる他人を求めているから。
一人で部屋にいるときですらそう感じていることもある。
まるで他人に四六時中監視でもされているかのように。
だからいつもどこか落ち着かず、気を静めるために他人を求める。
それでSNS中毒になったりもする。「いいね」がつくことが”気になる”。自分の発言が他人にどう見られたか”気になる”んだ。
人によっては私のように仮想的な他人の影を頭の中に作り出して、自分に否定的な目を向けて常に他人に見られている感覚を作り出したりするようなこともあるかもしれない。
頭の中に想像上の他人を作り出し、その他人に命令してもらったり、褒めてもらったり、ときにはけなされたりもする。
こうする理由は自分一人で何かをすると誰にも支配されていない、孤独であるという不安に襲われるから。
誰かに決めてもらったり、見てもらったり、正しいか間違っているか確認をしないとそれをしているのが恐ろしくてたまらない。
だから他人の代替的存在として影を作り出し、他人に言われたつもりで何かをしてしまうんだ。
他人、孤独への恐怖を打ち消す=承認欲求を満たす。
つまり承認欲求とは、他人や孤独に対して感じている恐怖の認知に対して、打ち消そうとする試みであるということ。
他人のいうことを聞くのも、褒められたいのも、
漠然とした他人に対する恐怖感が存在し、それを解消するための行為であるということ。
他人に対する”絶対視”
他人を怖いと思うことは、相手をなんらかの理由をもって恐怖の対象としているるということ。
例えば他人は自分よりも強いとか、優れているとか、脅威であるという思い込みがあることが前提だ。
あるいはその対極にある自分がおかしいとか、間違っているとか、劣っているといった前提である場合もある。
つまり他人のことを自身よりも「上の存在」であると思い込んでいることからもある。
故に、他人の言うことは絶対である、という思い込みができあがり、そこから派生して他人の言うことはすべて「正しい」と感じるようになり、自分のしていることはすべて「間違い」であると感じるようになる。
自分は他人に逆らってはならない。
おとなしく言うことを聞いていなければならない。
そうしなければ恐ろしい事が起こる。
だから孤独が怖い、他人が怖い。
他人に逆らったり間違えることそのものがすでに怖いことだから。
だからそれを取り除くために、踏み込まないために、
常に他人の承認を求めざるえないんだ。
落として、元に戻す思考
自分は常に間違っているという思い込みが前提にあるので、
何をするにも一旦自分を他人を使って「否定」する。
次に、その否定した何かに対して他人からの承認を求めるために行動し、それを得て自分を「肯定」する。
承認欲求というのはまずはじめに他人を使って自分を否定し、不安の感情に晒す。そしてその不安を他人の承認で解消する、という一連のプロセスで行動する欲求。
つまり、自分を一旦マイナスに下げたあとで、それを0に戻すということをやっているだけで、何もプラスがないんだ。
ただ自分をいじめて、落として、元の状態に戻す。そんなことをやっているだけである。
自分のやりたいことを持てない心理
この欲求に生きている限りは、決して自分のやりたいことができない。
より正確にはやろうとしても続かない。
なぜなら、たとえ自分のしたいことをみつけたとしても、全てが他人の都合を満たすためのものに変わってしまうから。
すべて他人というフィルターを通して行動してしまう。それは自分の素直な気持ちに嘘をつくことになる。
すべての行動、思考が他人の都合へと変化、義務化してしまうことで、
常に誰かに褒められないと、嫌われてしまうことをしているのではないかと感じて、不安になってやめてしまう。
自分が間違っているのではないかとおもってしまうから。他人の期待を満たせなくて無駄なことをしているのではないかと思ってしまうから。つまり、恐ろしいことをしているのではないか、と感じてしまうからである。
だから純粋に自分のしたいことを“持ち続ける”ことができず、無意識のうちに他人の都合にこたえられない自分という否定感に襲われて、続けることができなくなってしまうんだ。
承認欲求の正体とは?
自身を他人、孤独に対する恐怖の思い込みで突き動かし、他人からそれを癒やす安心を得る。
恐怖に突き動かされ他人を支配し、自分も他人もぎちぎちに縛って苦しめたうえで安心を得ようとする。
それが承認欲求という一連の思考形態。その正体。
承認欲求とは、これをくるくると回しながら日々を苦痛の中、不安の中で生き続ける、そんな常に他人ありきの、苦痛にあふれた生き方だ。
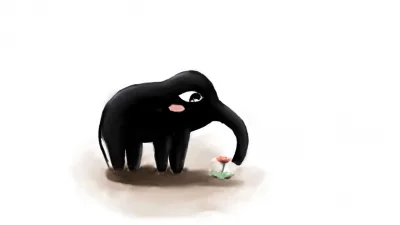
はじめまして!
おかげさまで承認欲求のカラクリがようやく理解できました。
1人の時間を作り自分軸になっても人と関わるとすぐに他人軸になっちゃう理由も上下関係に服従してきた恐れからパターンが蘇ってしまっていたんですね。
カラクリがわかったので視界がスッキリしました(*˙ᵕ˙ *)
elephanさんの書いて下さる内容がほんとにわかりやすぎてど真ん中すぎて(笑)ほんとにたくさんの気づきを頂いています。ありがとうございます(*^-^*)